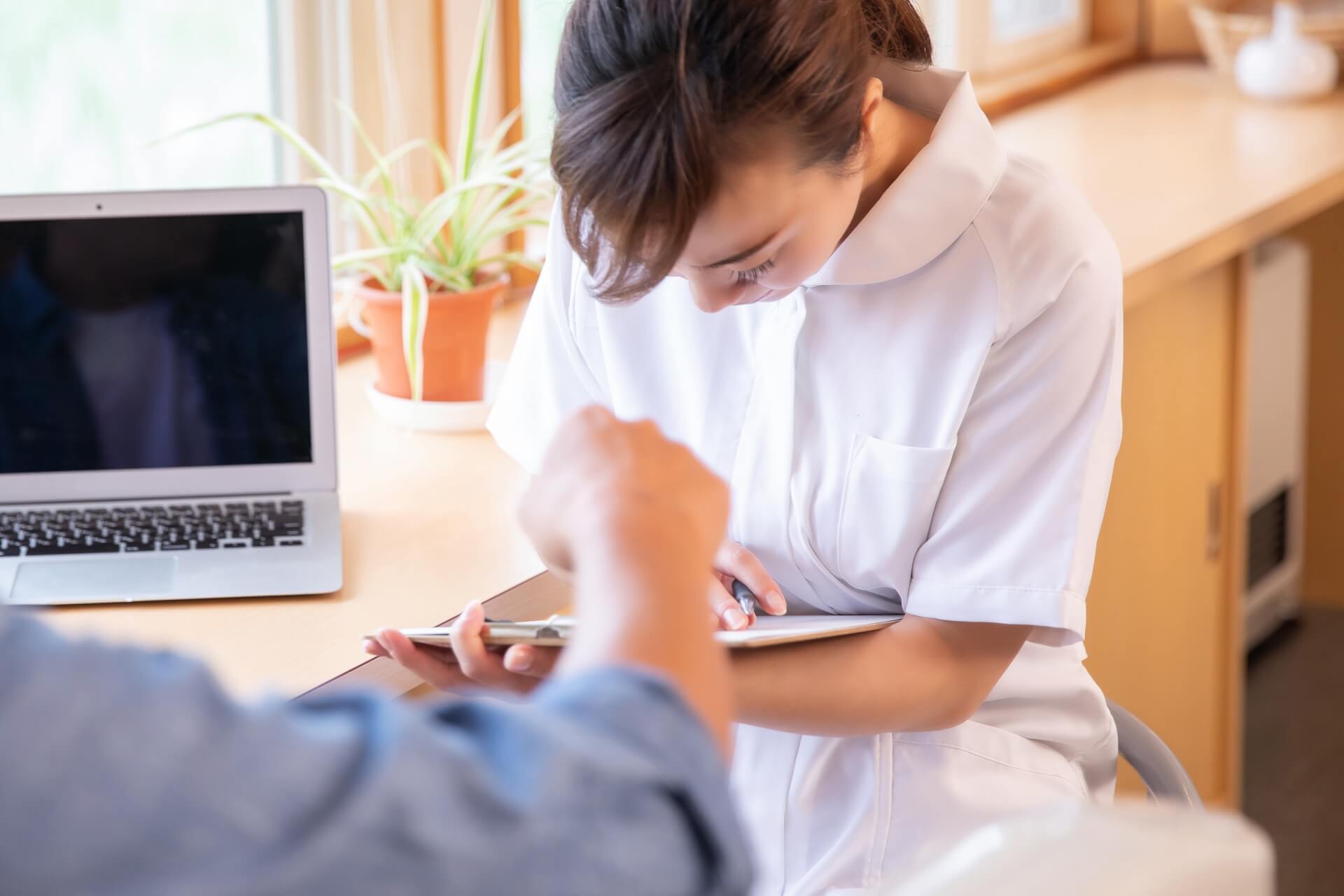2025.02.13

2025.02.13
ストレスマネジメントとは?やり方とストレス解消施策を解説
人事制度・組織づくり
人材教育
従業員が過度なストレスを抱えると、心身に不調をきたして休職や退職につながる可能性があります。 従業員の心身の健康を守り、生産性を高めるためには、企業としてストレスマネジメントに取り組むことが重要です。 本記事では、ストレスマネジメントが企業にもたらす効果や実践方法、注意点について紹介します。 企業が実施できる支援方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ストレスマネジメントとは ストレスマネジメントとは、ストレスを管理して上手に付き合っていく手法です。 適度なストレスはパフォーマンス向上に効果的とされていますが、業務や人間関係による過度なストレスは心身の不調につながる可能性があります。 従業員の心身の健康を守るためには、従業員一人ひとりがストレスマネジメントによって自身が抱えているストレスに気付き、適切に対処できるように企業が支援することが大切です。 ストレスマネジメントは、生産性やモチベーションの向上にもつながります。 ストレスを引き起こす原因 ストレスを引き起こす原因のことをストレッサーと呼びます。 ここでは、ストレッサーの種類を紹介します。 心理・社会的ストレッサー 心理・社会的ストレッサーとは、社会生活を送るうえで感じるストレス原因のことです。 例えば、職場の人間関係や仕事のプレッシャー、家庭不和や介護等のプライベートな問題がストレスの原因となります。 心理・社会的ストレッサーは、避けたり解消したりすることが難しいケースが多く、一般的にストレスと呼ばれるものの代表的な原因となっています。 物理・化学的ストレッサー 物理・化学的ストレッサーとは、温度や光、音、化学物質等の物理的な刺激のことです。 職場では、不快な室温や照度、騒音がストレスの原因となります。 ほかにも、タバコの臭いや薬品による刺激等がストレスの原因になることもあります。 物理・化学的ストレッサーは、精神的な負担だけでなく健康被害につながる可能性もあり、早期の解消が大切です。 生理・生物的ストレッサー 生理・生物的ストレッサーとは、人間の身体や病気に関連するストレス原因のことです。 例えば、睡眠不足や疲労、ウイルス感染等がストレスの原因となります。 生理・生物的ストレッサーによるストレスを防ぐためには、十分な休息を取り、感染対策を講じることが重要です。 ストレスマネジメントが職場に与える効果 ストレスマネジメントは、職場に以下のような効果をもたらします。 生産性やモチベーションを高められる ハラスメントの発生を防げる 休職者や離職者を減らせる それぞれ詳しく解説します。 生産性やモチベーションを高められる ストレスを抱えた従業員はパフォーマンスが低下するため、職場全体の生産性やモチベーションが下がってしまう可能性があります。 従業員がストレスと上手に付き合えるようになれば、生産性やモチベーションを高められます。 また、ストレスを解消して心身の健康を維持することで、業務に集中しやすくなり、ストレスが原因で生じるミスやトラブルも防止できるでしょう。 ハラスメントの発生を防げる 過度なストレスを抱えたまま仕事をしていると、怒りや不安な気持ちをコントロールできなくなり、ハラスメントが発生する可能性があります。 パワハラやセクハラが発生すると、生産性が低下するだけでなく、退職者の増加や企業イメージの低下につながるため注意が必要です。 ストレスマネジメントによってストレスを上手にコントロールすることで、従業員の気持ちに余裕が生まれ、職場の雰囲気がよくなるでしょう。 休職者や離職者を減らせる ストレスマネジメントには、休職者や離職者を減らす効果が期待できます。 ストレスを抱えた状態が続くと、心身に不調をきたして休職や退職につながってしまいます。 休職や退職で人員が減ると、ほかの社員の負担が増えたり、モチベーションが低下したりして退職希望者が連鎖的に増えてしまう可能性があり、注意が必要です。 新たな人員の確保には時間やコストがかかるため、ストレスマネジメントによって従業員の心身の健康を守りましょう。 ストレスマネジメントのやり方 ここからは、ストレスマネジメントの具体的なやり方を紹介します。 1.セルフモニタリングする まずは、自分の心身の状態を把握することが大切です。 ストレスの原因として考えられるものや気持ち、現れているストレス反応を紙に書き出してみましょう。 例えば、仕事量が多く、残業や休日出勤が増えてつらいときは、以下のように心身の状態を書き出します。 ストレス原因 仕事量が多い リラックスする時間が確保できない 気持ち 焦り 不安 イライラ ストレス反応 寝付きが悪い 食欲がない 日頃から自身のストレス原因やそのときの感情、ストレス反応を記録しておくことが大切です。 セルフモニタリングを通して自身のストレスの許容範囲を理解し、限界に達する前に対処しましょう。 2.ストレスコーピングを行う ストレスコーピングとは、ストレスへの対処方法のことです。ストレスを軽減するためには、原因に応じて適切な対処が大切です。 ここでは、主なストレスコーピングを3つ紹介します。 問題焦点型コーピング 問題焦点型コーピングとは、ストレスの原因そのものを解消しようとする方法です。 ストレスの原因が明確である場合や、改善できる見込みがある場合に有効な方法といえます。 例えば、仕事量が多くて残業が続いてストレスを感じている場合は、業務量を調整してもらったり、転職したりする行動が挙げられます。 情動焦点型コーピング 情動焦点型コーピングとは、ストレスの原因そのものを解消しようとするのではなく、自身の感情やとらえ方を変える方法です。 ストレスの原因によっては、すぐに改善するのが難しいケースもあるでしょう。 そのようなときに自身の感情やとらえ方を変えることで、ストレスが軽減することがあります。 例えば、不安や怒りを他者に話して発散したり、ストレスが自身の成長に必要であるといったポジティブなとらえ方をしたりする方法があります。 ストレス解消型コーピング ストレス解消型コーピングとは、ストレスの原因から離れて気晴らしをする方法です。 ストレスの原因に向き合うとさらにストレスが溜まることもあるため、距離を置くことも考えてみましょう。 例えば、趣味に没頭したり、食事を楽しんだりするのが効果的です。 ただし、ストレス解消方法としてやけ食いやギャンブルをすると、罪悪感で余計にストレスが溜まる可能性があるため、これらは避けましょう。 ストレスマネジメントをする際の注意点 ストレスマネジメントをするときは、ストレスをなくそうとしたり、一つの対処法にこだわったりしないことが大切です。 ストレスと上手に付き合うためにも、注意点を押さえておきましょう。 ストレスをゼロにしようとしない ストレスマネジメントは、あくまでもストレスを軽減するための手法です。 適度なストレスはモチベーションを維持するために必要なため、ゼロにしようとしないことが大切です。 例えば、プレッシャーを感じる仕事がストレスの原因になっているからといって、簡単にこなせる仕事ばかりしていると、やりがいを感じられなくなってしまいます。 ストレスマネジメントの際は、心身に不調をきたすほどの過度なストレスの軽減を意識しましょう。 一つの対処法に固執しない ストレスコーピングにはさまざまな種類があるため、一つの対処法にこだわらないことが大切です。 一つの対処法でストレスを軽減できなければ、ほかの方法も試してみましょう。 具体的には、上司に業務量の調整を申し出ても改善されなければ、自己成長につながるという考え方に変えたり、転職を検討したりしてみるのがよいでしょう。 企業ができるストレスマネジメントの支援方法 企業ができるストレスマネジメントの支援方法には、以下のような方法があります。 ストレスマネジメント研修の実施 ストレスチェックの実施 1on1ミーティングの実施 サポート体制の整備 それぞれ詳しく見ていきましょう。 ストレスマネジメント研修の実施 従業員がストレスマネジメントをするためには、やり方や適切なストレス解消方法を学ぶ必要があります。 従業員が正しい知識を身に付けるためにも、ストレスマネジメント研修を実施しましょう。 サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」では、管理職向けの「ストレスマネジメント力の強化」や、全社員向けの「メンタルヘルス・セルフケア」といったコンテンツを提供しています。 従業員にストレスとの付き合い方を学んでほしいと考えている方は、導入を検討してみましょう。 >>Cloud Campus「コンテンツパック100」をチェックする ストレスチェックの実施 ストレスチェックとは、従業員にストレスに関するアンケートを実施し、その結果を分析する取り組みです。 ストレスチェックには、自身が抱えているストレスに気付いたり、ストレスを抱えている従業員を見つけたりする効果があります。 また、ストレス原因を分析すれば、職場環境の課題解決につながることもあるでしょう。 従業員数が50人以上の企業では、2015年から年に1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。 50人未満の企業では努力義務となっていますが、従業員の心身の健康を守るためにも実施したほうがよいでしょう。 1on1ミーティングの実施 1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で対話することです。 1on1ミーティングを実施することで、部下が自身のストレスに気付くきっかけになります。 上司が部下にストレスを抱えていないか尋ねたり、一緒に対処法を考えたりする機会を設けましょう。 サポート体制の整備 ストレスによる休職や退職を防ぐには、従業員のストレスマネジメントをサポートすることが大切です。 従業員にストレスマネジメントを任せきりにするのではなく、会社として従業員のストレスに対してどのようなサポートができるか考えるようにしましょう。 外部の相談窓口を設置して、社内の人に相談しにくい悩みを相談できるようにサポートするのも効果的です。 まとめ 従業員が過度なストレスを抱えると、生産性の低下や退職者の増加につながる可能性があります。 そのような事態を防ぐためには、従業員がストレスマネジメントをできるようにサポートすることが大切になります。 ストレスとの付き合い方を学んでもらうためには、ストレスマネジメント研修の実施がお勧めです。 サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」では、管理職向けの「ストレスマネジメント力の強化」や、全社員向けの「メンタルヘルス・セルフケア」というコンテンツを提供しています。 従業員が自身のストレスに気付き、適切に対処できるように支援しましょう。 低コストで厳選コンテンツ見放題!コンテンツパック100 「コンテンツパック100」では、ストレスマネジメントに関するコンテンツを含む100以上のeラーニングコンテンツが見放題です。 1ID 年額999円(税抜)の低コストを実現しており、240社以上の企業で利用されています。 厳選されたニーズの高いコンテンツを、Cloud Campusのプラットフォーム上で研修としてすぐに利用可能です。 「コンテンツパック100」の詳細は、こちらからご確認いただけます。 >>Cloud Campus「コンテンツパック100」をチェックする

 サインイン
サインイン