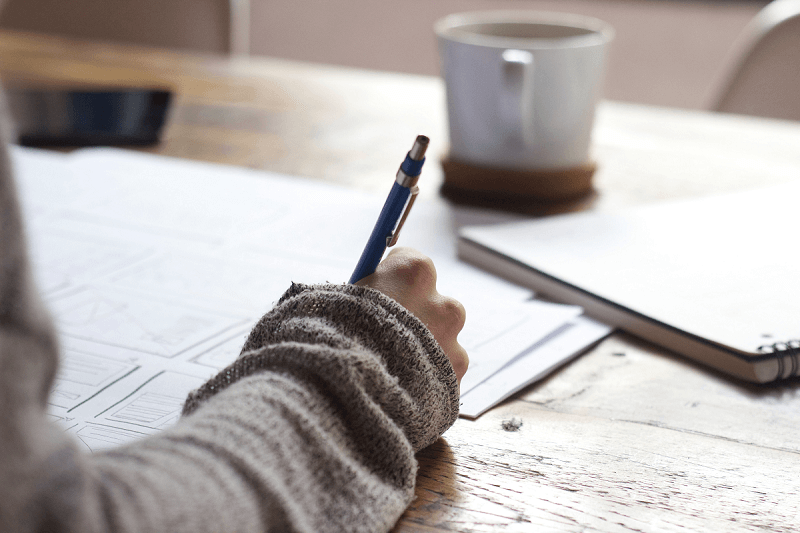2025.03.11
人材教育
- キーワード
-
- マネジメント
- 研修

優秀な管理職を育成して組織力を強化するためには、マネジメント研修の実施が効果的です。
マネジメント研修には、管理職が自身の役割を再認識したり、組織の生産性が向上したりする効果があります。
企業としての成長を続けるためにも、マネジメント研修を取り入れて組織力を高めていきましょう。
本記事では、マネジメント研修の内容や企業にもたらす効果を解説します。
実施時のポイントも紹介するので、マネジメント研修を取り入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
マネジメント研修とは
マネジメント研修とは、部下の管理や育成、組織力の強化といった組織マネジメントに必要なスキルを身に付けるための研修のことです。
マネジメント研修の主な目的は、人材マネジメントスキルや経営的視点をもった管理職を育成し、企業の業績向上を実現することです。
研修を受けた管理職が部下を育成したり、組織をまとめたりできる能力を身に付ければ、企業として成長し続けられる基盤が整うでしょう。
マネジメント研修は、日常業務で活用できるスキルを学べるだけでなく、管理職同士が意見や情報を交換する機会にもなります。
マネジメント研修の対象者
マネジメント研修の対象となるのは、以下のような社員です。
- 新任管理職:主任・チームリーダー等
- 中間管理職:課長・次長等
- 上級管理職:部長・本部長等
主任やチームリーダー等の新任管理職は、マネジメント研修を受講して管理職の役割を理解したうえで、基本的なスキルを身に付ける必要があります。
課長や次長といった中間管理職には、管理職としての役割を再認識したり、マネジメントスキルを高めたりするきっかけとして効果的です。
部長以上の上級管理職は、中間管理職との役割の違いを理解するだけでなく、ビジネス数字力やマーケティング力等の経営的視点を養うことが重要です。
マネジメント研修の内容と得られるスキル

マネジメント研修で得られる主なスキルは、以下の4つです。
- マネジメント力
- 育成力
- 組織強化力
- 経営的視点
それぞれ詳しく見ていきましょう。
マネジメント力
マネジメント研修では、組織を目標達成に導くマネジメント力について学びます。
チームをまとめるマネージャーには、スケジュール管理力やコミュニケーション力等のさまざまなスキルが求められます。
また、これらのスキルだけでなく、管理職の役割や重要性といった基礎知識も必要になります。
メンバーの能力を最大限活かせる組織づくりをするためにチームビルディングを学ぶのもよいでしょう。
マネジメントの経験を積んでいる中間管理職や上級管理職であっても、研修を受けることでより高いマネジメント力を身に付けられるようになります。
育成力
育成力は、部下の成長を促したり、モチベーションを維持したりするためのスキルです。
生産性の高い組織をつくるためには、一人ひとりの能力を高める部下育成力が求められます。
マネジメント研修では、管理職役と部下役に分かれてケーススタディを行い、多様な価値観をもつ部下へのフィードバック方法や、目標達成をサポートする方法が学べます。
研修で身に付けたスキルを活かして1on1ミーティングに取り組めば、部下の価値観や能力を把握しやすくなるでしょう。
組織強化力
組織強化力とは、従業員が企業目標を達成するために団結して力を発揮できる組織をつくるスキルのことです。
組織力の高い企業は、一人ひとりが能力を最大限に発揮できるため、大きな成果を挙げられます。
そのような組織をつくることができれば、突発的なトラブルや市場環境の変化にも対応しやすくなるでしょう。
マネジメント研修では、組織力を高めるための目標の共有方法や、コミュニケーションの取り方を学べます。
経営的視点
部長以上の上級管理職向けの研修では、ビジネス数字やマーケティング等の経営に関する知識を学びます。
上級管理職は、ビジネス数字から世の中の動きや業界の動向を把握したうえで、どのような戦略を取るべきかの判断力が求められます。
企業の利益を追求する経営的視点を身に付けるためにも、上級管理職に対してマネジメント研修を実施してみましょう。
マネジメント研修が企業にもたらす効果
マネジメント研修には、管理職としての自覚をもたせたり、生産性を高めたりする効果があります。
ここでは、マネジメント研修が企業にもたらす効果を解説します。
管理職としての自覚が生まれる
マネジメント業務をしたことがない新任管理職のなかには、自身が管理職であるという自覚をもてない方もいるはずです。
管理職になったときは、自分で成果を出すマインドから、組織として成果を出すというマインドに切り替える必要があります。
管理職としての自覚をもたずにプレイヤーとしての振る舞いを続けると、成果が出ない組織になってしまいます。
そのような意識を変えるためにも、管理職の役割や重要性を学ぶ機会を設けましょう。
マネジメント研修は、新任管理職だけでなく、既存管理職に役割を再認識させる場としても効果的です。
組織の生産性向上につながる
管理職が部下を適切に管理・育成できるようになれば、組織の生産性向上につながります。
上司の指示を待つ部下ばかりの組織では、ミスやトラブルが増えることで管理職の負担が大きくなってしまいます。
一人ひとりのメンバーが主体的に動く組織にするためには、マネジメント力が必要です。
管理職のマネジメント力を高めるためにも、マネジメント研修を活用してみましょう。
離職率の低下につながる
管理職がマネジメント力や育成力を身に付けると、離職率を低下させる効果が期待できます。
適切なマネジメントができれば、風通しがよいチームになり、メンバー同士のコミュニケーションも活発化します。
悩みや不安を打ち明けやすい環境になることで、メンバーが離職する前に対処できるようになるでしょう。
コミュニケーションが原因で離職するメンバーを出さないためにも、管理職が中心となって風通しのいい組織をつくることが大切です。
マネジメント研修を実施する際のポイント

マネジメント研修の効果を高めるためには、研修の目的を明確にしたりフォロー体制を整えたりすることが大切です。
ここでは、マネジメント研修を実施する際のポイントを紹介します。
研修の目的を示す
マネジメント研修を実施する際は、研修の目的や重要性を社員に理解してもらうことが大切です。
目的が理解できないまま進めると、研修の効果が薄れてしまいます。
マネジメント研修を実施する際は、何のために行うのか、どのような効果をもたらすのかを事前に共有するようにしましょう。
階級・タイミングにあった研修を選ぶ
マネジメント研修の効果を高めるためには、管理職の階級にあった内容を適切なタイミングで実施することが大切です。
管理職といっても、役職によって必要なスキルや悩みは異なります。
新任管理職に実施するときはマネジメントの基礎や部下育成に関する研修、部長以上の上級管理職にはビジネス数字力やマーケティング力等の経営的視点を身に付けられる研修が効果的です。
マネジメント研修を計画するときは、受講者が求めている知識やスキルを把握したうえでニーズにあったものを選びましょう。
研修後のフォローアップ体制を整える
マネジメント力は、研修を受講しただけで身に付くものではありません。
継続的に学び、実践してもらうためには、レポート提出や習熟度テスト、フォローアップ研修の実施が大切です。
フォローアップ研修とは、研修終了から一定期間が経過したタイミングに同じメンバーを集めて開催される研修のことです。
研修で学んだことが定着しているか、日常業務で実践できているかを振り返りながら、メンバー同士で情報交換やアドバイスをし合うことで、より理解が深まりやすくなります。
研修後のアンケートで効果測定を行い、より効率よく学べるように改善していくことも重要です。
マネジメント研修の実施方法
マネジメント研修の主な実施方法には、以下の3種類があります。
- 集合研修
- オンライン研修
- eラーニング
それぞれ詳しく解説します。
集合研修
集合研修は、講師と受講者が同じ会場に集まって実施する研修のことです。
対面での研修は、グループワークをしやすいので、具体的な場面を設定したロールプレイングを取り入れることも可能です。
社内の管理職が交流することで、業務がよりスムーズに進みやすくなるメリットもあります。
ただし、会場の確保やセッティング、関係者のスケジュール調整等の手間がかかります。
オンライン研修
オンライン研修は、パソコンやタブレットを利用してオンラインで実施する研修のことです。
オンライン研修を取り入れると、会場の手配が不要となり、会場の利用費がかかりません。
くわえて、会場までの移動が発生しないため、講師や受講者の移動時間やコストも削減できます。
働き方の多様化が進むなかで、集合研修に参加しにくい遠方で働く社員にも平等に研修の機会を与えられるのもうれしいポイントです。
ただし、対面に比べてグループワークをしにくかったり、参加者の通信環境を整える必要があったりするため、全てのケースでお勧めできる方法ではありません。
eラーニング
eラーニングとは、インターネットを利用したオンライン学習のことです。
会場の手配やスケジュール調整が不要で、時間や場所を問わず受講者の都合にあわせて実施できます。
eラーニングでは、自社で作成した研修資料や動画等のオリジナルコンテンツでの実施も可能です。
研修後のテストで受講者の理解度を集計できるため、効果測定が容易です。
ただし、グループワークを実施できなかったり、参加者の学習モチベーションを保つのが難しかったりするデメリットもあります。
マネジメント研修の効率を高めたいときは、eラーニング実施後に対面またはオンライン形式のフォローアップ研修を取り入れるのがお勧めです。
まとめ
企業が成長を続けるためには、部下を管理・育成し、組織力を強化できる管理職の育成が大切です。
組織マネジメントに長けた管理職が増えれば、組織の生産性が高まったり離職率が低下したりする効果を期待できます。
管理職のマネジメント力を高めるためにも、マネジメント研修を適切なタイミングで取り入れてみましょう。
サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」では、管理職向けの「組織マネジメント力の強化」や「部下のキャリア開発」等のマネジメントに関するコンテンツをeラーニングで学べます。
忙しい管理職に組織マネジメントを身に付けてもらうためにも、eラーニングを活用してみましょう。
低コストで厳選コンテンツ見放題!Cloud Campusコンテンツパック100
サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」は、マネジメント研修に関するコンテンツを含む、100以上のeラーニングコンテンツが見放題です。
ニーズの高いコンテンツを厳選することで、業界最安値の1ID 年額999円(税抜)を実現しており、利用企業は240社を超えています。
Cloud Campusのプラットフォーム上で研修としてすぐに利用可能です。
「Cloud Campusコンテンツパック100」の詳細は、以下からご確認頂けます。

 サインイン
サインイン