2025.07.18
ITスキル
- キーワード
-
- AI
- 機会学習
- ディープラーニング

AI・機械学習の導入を検討している方のなかには、「AIと機械学習、ディープラーニングは何が違うのか」「どのような場面で活用できるのか」といった疑問をもっている方もいるのではないでしょうか。
AI・機械学習を効果的に活用するためには、それぞれの概要や活用シーンを理解しておくことが大切です。
本記事では、AIと機械学習の違いや活用事例、導入手順を解説します。導入する際のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
AIとは
AIとは「Artificial Intelligence」の略称で、人間の知能をコンピュータ上で再現しようとする技術のことです。AIを活用すれば、言語理解や画像認識、問題解決といった人間がする知的作業をコンピュータが実行できるようになります。
AIは、特定のタスクを担ったり、人間では処理しきれない大量のデータからパターンを見つけ出したりすることで、日常生活やビジネスに変化をもたらしています。
機械学習とは
機械学習とは、データからパターンを学習し、判断や予測ができるようになる技術のことです。
機械学習には、以下の3種類があります。
- 教師あり学習
- 教師なし学習
- 強化学習
それぞれ詳しく解説します。
教師あり学習
教師あり学習とは、入力データとデータに対応する正解(教師データ)を与えて学習させる方法です。例えば「この写真には犬が写っている」「このメールはスパムメールである」といった、あらかじめ正解になり得るデータを用いて学習させます。
学習が完了すると、未知の入力データに対しても正解を予測できるようになります。教師あり学習の代表的な活用例は、画像認識やスパムメール判定等です。
教師なし学習
教師なし学習とは、正解が与えられていないデータから構造やパターンを発見する学習方法です。人間が想定していなかったような隠れたパターンや関係性を見つけ出せるのが特長です。
教師なし学習は、顧客の購買履歴から類似する行動パターンをもつグループを自動的に見つけ出して分類する場面に役立ちます。教師あり学習と異なり、正解データを用意する必要がないため、データ準備にかかる手間を軽減できます。
強化学習
強化学習とは、AIが試行錯誤を繰り返しながら最適な行動を学習する手法です。
AIが自ら行動し、報酬という形でフィードバックを受け取ることで、より多くの報酬が得られる行動を学習します。
強化学習は、自律的な意思決定が求められる分野に活用可能です。代表的な活用例として将棋AIや自律移動ロボット、自動運転車等が挙げられます。
AIと機械学習の違い
AIは、人間の知能をコンピュータで再現しようとする技術です。
一方の機械学習は、AIを実現するための手段の一つです。
具体的には、自動運転を実現するためには、道路標識や他の車を認識する「画像認識」や、運転中のさまざまなデータから事故の可能性を予測する「危険予知」といった機械学習が必要となります。
機械学習によって学習されたモデルは、AIシステムの一部として組み込まれるため、機械学習はAIの一分野であるといえます。
機械学習とディープラーニングの違い
ディープラーニングとは、機械学習の分野の一つです。
人間の脳の神経回路を再現した「深層ニューラルネットワーク」を使ってデータから自動で特徴を見つけ出し、高度な判断をする技術のことです。
機械学習とディープラーニングの主な違いは、人間が特徴量を設定する必要があるかという点です。
特徴量とは、データ分析の対象となるデータの特徴を処理しやすくなるように定量的な数値にしたものをいいます。
機械学習では、データから「どのような特徴」を学習させるかを人間が設定しなければなりません。例えば、犬の画像を判別する際に「耳の形」や「毛並み」といった特徴を人間が指示します。
一方、ディープラーニングでは、コンピュータがデータから自動的に特性を見つけ出すことが可能です。犬と猫の画像認識を例にすると、ディープラーニングでは犬らしい部分や猫らしい部分をコンピュータが学習し、特徴を見つけ出して判別します。
AI・機械学習の活用事例
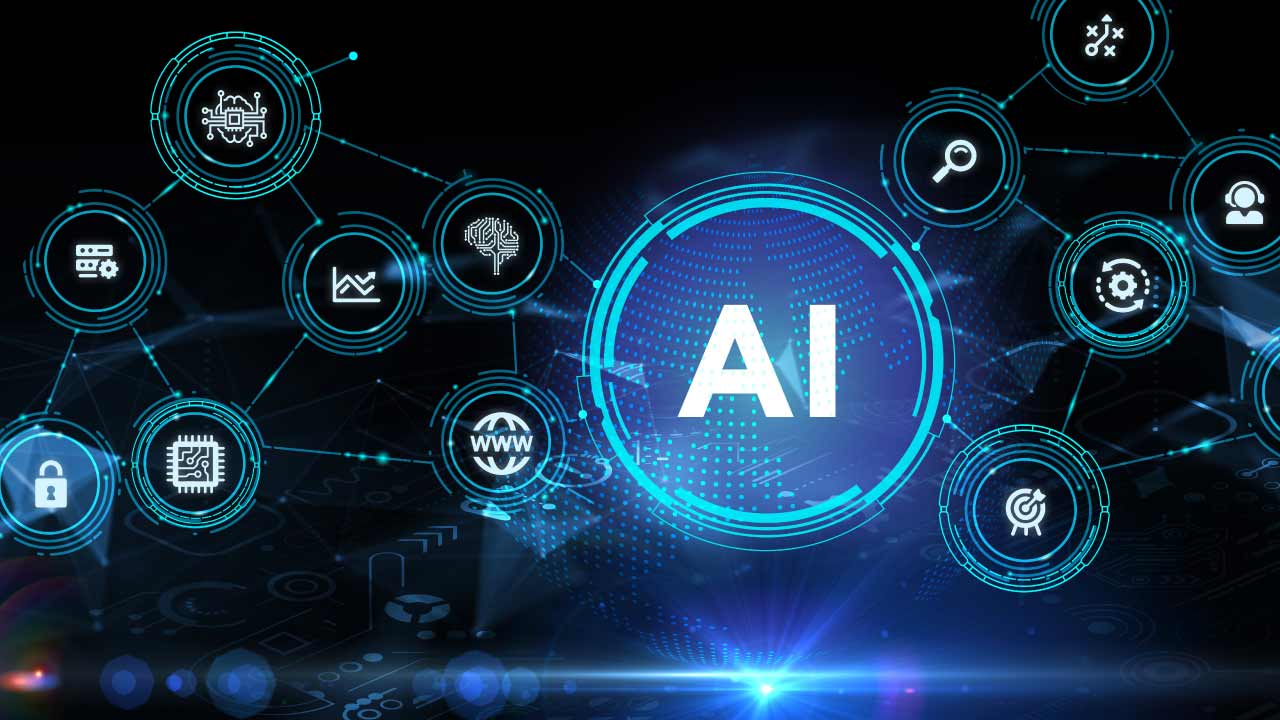
AI・機械学習は、さまざまな業界で活用され、ビジネスに変革をもたらしています。
ここでは、AI・機械学習の活用事例を紹介します。
小売業における需要予測
小売業では、AIと機械学習が商品の需要予測に活用されています。AIが過去の販売データや季節、天候等の要因を分析して販売予測数を提示することで、適切なタイミングで必要な量を仕入れられるようになり、過剰在庫や品切れを防げます。
店舗の繁忙日時を予測することもでき、効率的な人員配置にも役立つでしょう。
製造業における品質管理・予知保全
製造業では、AIと機械学習が品質向上や設備の安定稼働に貢献しています。
製品画像をAIが解析し、人間の目では見落としがちな細かな欠陥を検出することで、品質管理の精度を高めています。また、稼働中の機械の振動や温度、電流といったデータを継続的に分析し、部品の劣化や故障の兆候を早期に検知することも可能です。
計画的なメンテナンスや部品交換ができれば、予期せぬ設備停止を防ぐことができるでしょう。
金融業における融資審査・不正検知
金融業界では、AIと機械学習が融資審査の効率化や不正取引の防止に役立てられています。
顧客の信用情報や財務データをAIが分析し、融資の可否を判断することでスピーディーな審査を可能にしています。さらに、大量の取引データをAIがリアルタイムで分析し、通常と異なる取引を自動的に検知することによって、クレジットカードの不正利用やマネーロンダリングといった金融犯罪を未然に防ぐことも可能です。
医療支援
医療分野では、AI・機械学習が診断精度の向上や医療従事者の負担軽減に貢献しています。具体的には、X線やMRI等の画像診断において病変を検出したり、疾患の早期発見を支援したりすることが可能です。
また、患者の遺伝子情報や過去の症例といったデータから疾患の可能性を提示し、最適な治療法を提案する個別化医療も進んでいます。
カスタマーサポート
カスタマーサポートでは、AIと機械学習が顧客対応の効率化と顧客満足度向上に貢献しています。
代表的な活用例は、顧客からの問い合わせに自動で対応するチャットボットです。自然言語処理技術を用いて顧客の質問を理解し、適切な回答を提示します。顧客からの問い合わせに24時間365日の対応が可能となり、簡単な問い合わせをAIが処理することで、オペレータの負担軽減につながっています。
企業がAIと機械学習を導入するメリット
企業がAIと機械学習を導入するメリットは、以下の3つです。
- 業務効率が向上する
- 競争力強化につながる
- リスクを軽減できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務効率が向上する
AI・機械学習を導入すれば、問い合わせ対応やデータ入力、品質検査、需要予測、在庫管理といった定型業務や反復作業を自動化できます。AIに単純作業を任せることで他の業務に時間を使えるようになるだけでなく、人的ミスを減らしたり、生産性が向上したりすることにつながります。
その結果、従業員はより創造的な業務に集中できるようになるため、モチベーションアップにもつながるでしょう。
競争力強化につながる
AI・機械学習は、人間では処理しきれない大量のデータから、隠れたパターンや傾向を見つけ出すことが可能です。企業がAI・機械学習を導入すれば、データに基づいた意思決定ができるようになり、ビジネスチャンスをいち早く捉えられるようになります。
例えば、過去の販売データやSNSでの顧客の意見といった膨大な情報をAIに取り込めば、新製品開発の方向性を定めたり、需要に応じた生産計画を立てたりすることができます。
また、顧客の購買履歴や行動パターンの分析により、最適なマーケティング戦略を立案することも可能です。
AI・機械学習を活用して市場の変化にすばやく対応できるようになれば、競合他社との差別化を図れるでしょう。
リスクを軽減できる
AI・機械学習の導入は、ビジネスにおけるリスクを早期に発見し、被害を未然に防ぐことにもつながります。例えば、人間の目では見逃してしまう小さな欠陥を検出することで、不良品によるクレームやリコールのリスクを軽減できたり、不正取引のリアルタイム検知によって被害を防いだりすることが可能です。
AI・機械学習の導入により、予期せぬトラブルや損失から企業を守ることもできるでしょう。
AIと機械学習を導入する流れ

AIと機械学習を導入する流れは、以下の通りです。
- AIと機械学習で解決したい課題を明確にする
- データを収集する
- 小規模なシステムで検証する
- 運用する
- 効果測定と改善をする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.AIと機械学習で解決したい課題を明確にする
AIと機械学習を導入する際は、解決したい課題を明確にすることが重要です。「業務効率化のため」といった漠然としたものではなく、「検査時間を20%短縮したい」「問い合わせ対応時間を30%短縮したい」といった具体的な目標を設定しましょう。
課題や目標が明確になったら、AI・機械学習の導入が課題に適しているのかを慎重に検討することが大切です。既存の業務プロセスの見直しや、別のIT技術の導入のほうが効果的な場合もあります。無駄な投資を避けるためにも、AI・機械学習の導入効果を見極めましょう。
2.データを収集する
AIを活用するためには、学習させるためのデータが必要不可欠です。解決したい課題に応じて必要なデータの種類、量、形式を洗い出し、計画的に収集しましょう。需要予測をしたいのであれば、過去の販売データや天候データ、イベント情報等が必要となります。
データを集める際は、量だけでなく質にもこだわりましょう。不正確だったり、偏りのあるデータでは、AIが誤った学習をしてしまい、期待する効果が得られない可能性があります。
また、個人情報や機密情報を含むデータを扱う際は、プライバシー保護やセキュリティ対策を徹底し、法的規制や社内ポリシーの遵守が重要です。
3.小規模なシステムで検証する
まずは、一部の業務プロセスや特定の部署に限定して、小規模なシステムでAIが実際に課題解決に貢献できるかを検証しましょう。
設定した目標に対し、AIが期待する効果を発揮できるのか、導入コストが効果に見合うのかといった点を評価します。期待する効果が得られない場合は、データの見直しや別の課題への適用を検討する必要があるでしょう。
4.運用する
小規模な検証で効果が確認できたら、AIモデルを既存の業務システムやデータベースと連携させ、本格的な運用を開始します。AIを効果的に使いこなせるように、従業員のトレーニングやサポート体制の構築も進めましょう。
5.効果測定と改善をする
AI導入後も、継続的な効果測定と改善が必要です。設定した目標に対してAIがどの程度の効果を発揮しているかを定期的に評価しましょう。
環境の変化や新たなデータの蓄積にともない、AIのパフォーマンスが低下することがあります。最適なパフォーマンスを維持できるように、必要に応じて再学習させたり、アルゴリズムを改善したりしましょう。
AI・機械学習を導入する際のポイント

AI・機械学習を導入する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 費用対効果を確認する
- 専門人材を採用・育成する
- 関連法令やガイドラインを遵守する
それぞれ詳しく解説します。
費用対効果を確認する
AI・機械学習を導入するには、システム開発費や運用費等のまとまった費用がかかります。導入前に費用対効果を試算し、ビジネス上のメリットが費用を上回るのか確認することが重要です。例えば、AIによるデータ入力の自動化を検討するのであれば、手作業による現状のコストと、AI導入後の人件費削減や生産性向上の効果を比較しましょう。
専門人材を採用・育成する
AIを効果的に活用していくためには、専門知識を有する人材が必要です。専門人材を確保する方法として外部からの採用が有効であるものの、競争が激しくコストも高くなりがちです。そのため、外部からの採用だけでなく、既存社員の育成も視野に入れるようにしましょう。
既存社員は自社の業務プロセスやデータに精通しており、AI技術を習得することで効果的な活用が期待できます。既存社員を育成するためには、研修の実施がお勧めです。
サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」の「AIリテラシー入門」では、AIに関する基礎知識を全16のテーマに分けてeラーニングで学べます。「コンテンツパック100」の詳細は、以下からご確認頂けます。
>>Cloud Campus「コンテンツパック100」をチェックする
関連法令やガイドラインを遵守する
AIを活用する際は、関連法令やガイドラインを遵守することが大切です。また、AI学習に利用するデータに個人情報や機密情報が含まれる場合は、プライバシー保護やセキュリティ対策を徹底しなければなりません。個人情報や機密情報の無断使用や漏洩は、訴訟や企業の信頼失墜につながるため、細心の注意を払いましょう。
また、AIの判断が特定の属性に偏見をもたないように、公平性を保つことも重要です。偏りのあるデータを学習させると、AIが差別的な結果を生み出す可能性があります。
データ収集の段階からデータに偏りがないかを入念にチェックし、アルゴリズムの設計にも注意して公平性を保ちましょう。
AIと機械学習の役割を理解したうえで導入を検討しよう
AI・機械学習の導入は、業務効率の向上や競争力の強化、リスク軽減等、企業に多くのメリットをもたらします。しかし、解決したい課題によっては、業務プロセスの見直しや他のIT技術の導入のほうが有効である可能性もあります。
AI・機械学習の役割を理解し、課題解決に対する最適な方法であることを確認したうえで導入を検討しましょう。
AI・機械学習を導入する際は、従業員のAIリテラシーの向上が必要となります。サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」の「AIリテラシー入門」では、AIに関する基礎知識を全16のテーマに分けてeラーニングで学べるため、AIに関する知識を深めるのに役立てられます。
低コストで厳選コンテンツ見放題!Cloud Campusコンテンツパック100

サイバー大学の「Cloud Campusコンテンツパック100」は、AIに関するコンテンツを含む、100以上のeラーニングコンテンツが見放題です。
ニーズの高いコンテンツを厳選することで、業界最安値の1ID 年額999円(税抜)を実現しており、利用企業は240社を超えています。
Cloud Campusのプラットフォーム上で、研修としてすぐに利用可能です。
「Cloud Campusコンテンツパック100」の詳細は、以下からご確認頂けます。

 サインイン
サインイン





